リハビリテーション医学研究部
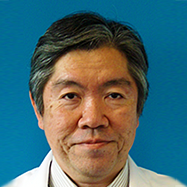
部長 惠飛須 俊彦
Director Toshihiko Ebisu, MD, PhD
関西電力医学研究所 リハビリテーション医学研究部 部長
関西電力病院 リハビリテーション科 部長
研究部概要
リハビリテーション医学研究部では、高齢障害者および脳血管障害者の効果的なリハビリテーションの確立に向けて、運動療法、栄養療法の効果を様々な角度のデータから検証し、研究を行っています。
また、各臓器障害の急性期・回復期に対する効果的なリハビリテーションの確立に向けても、物理療法・運動療法・高次脳機能訓練など様々なリハビリテーションの治療手技の効果を検証して、研究を行っています。
研究テーマ
①脳血管障害者の回復期リハビリテーションにおける脳領域間functional
connectivityの変化について
近年 安静時fMRI (resting state
fMRI)すなわち認知課題を遂行せず、安静時に撮像するfMRIを用いて、脳領域間の機能的結合(functional
connectivity)の測定が可能であることが報告され、脳は安静時も休止しているのではなく、絶えず自発的な神経活動は行っており、それに基づくBOLD信号の揺らぎが生じ、その揺らぎに着目すると異なる領域間の自発的神経活動の相関関係を機能的結合と呼び、領域間の機能的なコミュニケーションを反映するものと考えられている。安静時fMRIは、認知的あるいは身体的に課題遂行が困難な患者様の脳内ネットワークの検出に有用な手法と思われる。また、MRIでは分子拡散の異方性情報を使って神経繊維追跡を行いtractography
(DTI)を作成することも容易に行えるようになってきた。筆者は1991年より分子拡散を用いた脳疾患病態解析の分野での研究、発表を多数行ってきた。一方、日常リハビリテーションの現場では、完全麻痺を有する症例でも、装具装着し、積極的立位・歩行訓練を継続することにより、動作能力の改善を獲得することはよく経験する。また高次脳機能についても、半側空間無視など、リハビリテーションに伴い改善が見られる症例も臨床現場で経験する。すでに損傷を受けた神経細胞の再生は一般的に困難と言われてきたが、ここ数年、脳内ネットワーク再構築に関する報告もなされはじめてきている。しかしながら、まだ報告は少なく、高次脳機能を含めた回復過程における新たな脳内ネットワークの構築の関与の可能性など、リハビリテーションの効果の科学的解明に関する研究はまだ多くは行われていない。
脳血管障害患者のリハビリテーションによる機能回復課程において、積極的装具療法による歩行機能を中心とした運動機能の改善と脳内ネットワークの変化との関連を検討する。また、半側空間無視など視空間認知の障害の回復過程にも注目し、認知機能の改善と脳内ネットワークの変化との関連についても検討する。当院回復期リハビリ患者様を対象とし、回復期病棟入院時および退院前に3テスラMRI装置を用いてfMRIおよびDTIを撮像する。fMRI解析は起点相関法
(seed-based correlation
method)で施行し、DTI解析ではtractography作成を行って検討する。解析は生理学研究所(岡崎)特任教授 福永PhDとの共同研究として行う。
②超高齢化社会での自動車運転者における認知機能の画像評価システムの開発
超高齢社会の到来に伴い、高齢者の認知機能低下が社会に及ぼす影響は重大である。近年、高齢者の自動車運転における操作ミスによる事故の報道があとを絶たず、自動車メーカー側による自動運転など自動車機能の改良の試みはなされているものの、運転者側の対策は未だ十分になされていない。認知機能は、いわば電気回路のような脳内領域間の内在的配線におけるネットワーク機能の低下と関連していると考えられ、脳内領域間の機能的結合の状態を画像で評価することができれば、高齢者脳ドックや自動車運転免許更新時などで、注意機能、遂行機能、記憶機能などの自動車運転に必要な認知機能を画像的に評価することが可能となる。本研究では、安静時脳機能MRI画像及び拡散テンソル画像を用いて脳内領域間の機能的結合について画像データバンクを作成することにより、超高齢社会での自動車運転者における認知機能についての画像評価システムを確立する。解析は生理学研究所(岡崎)特任教授 福永PhDとの共同研究として行う。
③半側空間無視におけるバーチャルリアリティを活用したトレーニング効果
半側空間無視とは、脳卒中後に病巣と反対側の空間の刺激に対する反応の欠如または遅延を特徴とする症候であり、日常生活動作の自立を困難にする。
半側空間無視の症状改善を目的として、バーチャルリアリティを活用したトレーニング効果を検証する。このトレーニングにより、半側空間無視の日常生活における症状改善と、左空間の反応時間が短縮に効果的であったことを明らかにする。
最近の代表的な論文
| 著者 | 論文題目 |
|
Ebisu T, Fukunaga M, Murase T, Matsuura T, Tomura N, Miyazaki Y, Osaki S, Okada T, Higuchi T, Umeda M. |
Functional Connectivity Pattern Using Resting-state fMRI as an Assessment Tool for Spatial Neglect during the Recovery Stage of Stroke: A Pilot Study. Magn Reson Med Sci 2023, 22:313-324. doi: 10.2463/mrms.mp.2022-0010. |
| Osaki S, Amimoto K, Miyazaki Y, Tanabe J, Yoshihiro N |
Reaction time analysis in patients with mild left unilateral spatial neglect employing the modified Posner task: vertical and horizontal dimensions.Exp Brain Res. 2022 Aug;240(7-8):2143-2153. doi: 10.1007/s00221-022-06400-z. |
2024年度業績
原著論文(英語/日本語)
| 著者 | タイトル | 掲載誌名 |
| 掲載号等・掲載年 | ||
| Osaki S, Amimoto K, Miyazaki Y, Tanabe J, Yoshihiro N |
Effect of stimulation-driven attention in virtual reality balloon search training of patients with left unilateral spatial neglect after stroke: A randomized crossover study. |
Neuropsychol Rehabil |
|
2024 Oct;34(9):1213-1233. doi: 10.1080/09602011.2023.2236350. Epub 2023 Jul 21 |
||
| 山本洋司 | 両側大腿骨三重骨折(転子下・骨幹部・顆部)1例における観血的骨接合術後の理学療法経験 | 理学療法ジャーナル 58(2) 241-245, 2024 |
| 山本洋司、渡辺広希、児島範明、高田祐輔、松木良介 | 経頭蓋カラードプラ法による早期立位時の脳血流動態評価を基に安全な早期離床が実施可能であった急性期くも膜下出血3例 | 理学療法学 51(4) 125−132 2024 |
| 山本洋司 渡辺広希 児島範明 松木良介 |
急性期くも膜下出血患者における経頭蓋カラードプラ法を用いたHead up tilt時の脳血流評価 |
理学療法学 52(4) 71−78 2024 |
総説(日本語)
| 著者 | タイトル | 掲載誌名 |
| 掲載号等・掲載年 | ||
| 尾崎 新平、網本 和 | 【ここがポイント!半側空間無視のリハビリテーション診療】半側空間無視に対する理学療法のポイント | Medical Rehabilitation |
| No.298 Page32-37(2024.03) |
メンバー
| 部長 | 惠飛須 俊彦 |
|---|---|
| 上級特別研究員 | 藤本 康裕 (リハビリテーション医学研究部 (兼)臨床教育・研修センター) |
| 上級特別研究員 | 宮崎 泰広 |
| 上級特別研究員 | 尾崎 新平 |
| 特別研究員 | 山本 洋司 |
| 特別研究員 | 堀田 旭 |
| 特別研究員 | 平澤 良和 |
| 研究員 | 平野 博久 |
| 研究員 | 高崎 盛生 |
| 研究員 | 渡辺 広希 |
| 研究員 | 飯山 幸治 |
| 研究員 | 砂原 正和 |
| 研究員 | 高松 賢司 |